|
第1節 計画の目的 |
|
1 計画の目的 この計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づき、山形村防災会議が作成する計画であって、村、関係機関、住民等が相互に協力し、村の地域に係る災害予防対策、災害応急対策、災害復旧・復興対策を推進することにより、村域における土地の保全とかけがえのない住民の生命、身体及び財産を保護することを目的とする。 【国、県及び山形村の防災会議並びに防災計画の体系】 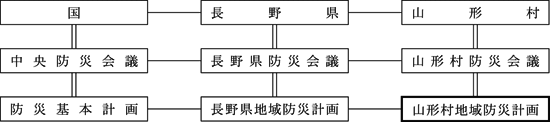
2 計画の基本方針 (1) 防災対策の実施 防災対策の実施に当たっては、次の事項を基本とし、村、県、その他関係機関及び住民がそれぞれの役割を認識しつつ、一体となって最善の対策をとるものとする。特に、災害時の被害の最小化と被害の迅速な回復を図る「減災」を基本理念とし、たとえ被災しても人命を守ることを最重視するとともに、経済的被害をできるだけ少なくするため、さまざまな対策を組み合わせて災害に備え、災害時の社会経済活動への影響を最小限にとどめるよう、対策の一層の充実を図る。 ア 周到かつ十分な災害予防 (ア) 災害予防段階における基本理念は以下のとおりである。 a 災害の規模によっては、ハード対策だけでは被害を防ぎきれない場合もあることから、ソフト施策を可能な限りすすめ、ハード・ソフトを組み合わせて一体的な災害対策を推進する。 b 最新の科学的知見を総動員し、起こり得る災害及びその災害によって引き起こされる被害を的確に想定するとともに、過去に起こった大規模災害の教訓を踏まえ、絶えず災害対策の改善を図ることとする。 (イ) 災害予防段階における施策の概要は以下のとおりである。 a 災害に強いむらづくりを実現するため、主要交通・通信機能の強化、避難路の整備、学校、医療施設等の公共施設や住宅等の建築物の安全化、代替施設の整備等によるライフライン施設等の機能の確保策を講じる。 b 事故災害を予防するため、事業者や施設管理者による情報収集・連絡体制の構築、施設・設備の保守・整備等安全対策の充実を図る。 c 住民の防災活動を促進するため、防災教育等による防災思想・防災知識の普及、防災訓練の実施等を行う。併せて、自主防災組織等の育成強化、防災ボランティア活動の環境整備、事業継続体制の構築等企業防災の促進、災害教訓の伝承により住民の防災活動の環境を整備する。 d 防災に関する研究及び観測等を推進するため、防災に関する基本的なデータの集積、工学的、社会学的分野の研究を含めた防災に関する研究の推進、予測・観測の充実・強化を図る。また、これらの成果の情報提供及び防災施策への活用を図る。 e 発災時の災害応急対策、その後の災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行うため、災害応急活動体制や情報伝達体制の整備、施設・設備・資機材等の整備・充実を図るとともに、必要とされる食料・飲料水等を備蓄する。また、関係機関が連携した実践的な訓練や計画的かつ継続的な研修を実施する。 イ 迅速かつ円滑な災害応急対策 (ア) 災害応急段階における基本理念は以下のとおりである。 a 発災直後は、可能な限り被害規模を早期に把握するとともに、正確な情報収集に努め、収集した情報に基づき、生命及び身体の安全を守ることを最優先に、人材・物資等災害応急対策に必要な資源を適切に配分する。 b 被災者のニーズに柔軟かつ機敏に対応するとともに、高齢者、障がい者、児童、傷病者、外国籍住民、外国人旅行者、観光客、乳幼児、妊産婦など特に配慮を要する者(以下「要配慮者」という。)に配慮するなど、被災者の年齢、性別、障がいの有無といった被災者の事情から生じる多様なニーズに適切に対応する。 (イ) 災害応急段階における施策の概要は以下のとおりである。なお、災害応急段階においては、関係機関は、災害応急対策に従事する者の安全の確保を図るよう十分配慮するものとする。 a 災害発生の兆候が把握された際には、警報等の伝達、住民の避難誘導及び所管施設の緊急点検等の災害未然防止活動を行う。 b 発災直後においては、被害規模を早期に把握するとともに、災害情報の迅速な収集及び伝達、通信手段の確保、災害応急対策を総合的、効果的に行うための関係機関等の活動体制及び大規模災害時における広域的な応援体制を確立する。 c 被災者に対する救助・救急活動、負傷者に対する迅速かつ適切な医療活動、消火活動を行う。 d 円滑な救助・救急、医療及び消火活動等を支え、また被災者に緊急物資を供給するため、交通規制、施設の応急復旧、障害物除去等により交通を確保し、優先度を考慮した緊急輸送を行う。 e 被災状況に応じ、指定避難所の開設、応急仮設住宅等の提供、広域的避難受入活動を行う。 f 被災者等へ的確かつ分かりやすい情報を速やかに公表・伝達するとともに、相談窓口の設置等により住民等からの問い合わせに対応する。 g 被災者の生活維持に必要な食料・飲料水及び生活必需品等を調達し、被災地のニーズに応じて供給する。 h 指定避難所等で生活する被災者の健康状態の把握等のために必要な活動を行うとともに、仮設トイレの設置等被災地域の保健衛生活動、防疫活動を行う。また、遺体の処置は速やかに行う。 i 社会秩序の維持のため防犯活動等を実施するとともに、物価の安定・物資の安定供給のための監視・指導等を行う。 j 応急対策を実施するための通信施設の応急復旧、二次災害を防止するための土砂災害等の危険のある箇所の応急工事、被災者の生活確保のためのライフライン等の施設・設備の応急復旧を行う。二次災害の防止策については、危険性の見極め、必要に応じた住民の避難及び応急対策を行う。 k ボランティア、義援物資・義援金を適切に受け入れる。 ウ 適切かつ速やかな災害復旧・復興 (ア) 災害復旧・復興段階における基本理念は以下のとおりである。 a 発災後は、速やかに施設を復旧し、被災者に対して適切な援護を行うことにより被災地の復興を図る。 (イ) 災害復旧・復興段階における施策の概要は以下のとおりである。 a 被災の状況や被災地域の特性等を勘案し、被災地域の復旧・復興の基本方向を早急に決定し、事業を計画的に推進する。 b 災害により生じた廃棄物(以下「災害廃棄物」という。)の広域処理を含めた処分方法の確立と、計画的な収集、運搬及び処理により、適正かつ迅速に廃棄物を処理する。 c 災害の防止とより快適な生活環境を目指して、災害に強いむらづくりを実施する。 d 被災者に対する資金援助、住宅確保、雇用確保等による自立的生活再建を支援する。 e 被災した中小企業の復興等、地域の自立的発展に向けて経済復興を支援する。 (ウ) 村は、県、防災関係機関と、互いに連携をとりつつ、これら災害対策の基本的事項について推進を図るとともに、防災機関間、住民等の間、住民等と行政の間で防災情報が共有できるように必要な措置をとる。 (2) 村及び関係機関等が行うべき事項 村及び関係機関等は、緊密な連携のもと、人命の安全を第一に、次の事項を基本とし、必要な措置をとる。 ア 要配慮者を含めた多くの住民の地域防災活動への参画 イ 地域における生活者の多様な視点を反映した防災対策の実施により地域の防災力向上を図るため、防災会議の委員への任命など、防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現場における女性や高齢者、障がい者などの参画を拡大し、男女共同参画その他の多様な視点を取り入れた防災体制を確立 (3) 住民が行うべき事項 住民は、「自分の命は自分で守る」との認識のもと、地域、職場、家庭等において互いに協力し合い、災害時を念頭においた防災対策を平常時から講じる。 また、どこでも起こりうる災害時の被害を最小化し、安全・安心を確保するためには、行政による公助はもとより、個々人の自覚に根ざした自助、身近な地域コミュニティ等による共助が必要であり、個人や家庭、地域、企業、団体等社会の様々な主体が連携して日常的に減災のための行動と投資を息長く行う運動を展開する。また、その推進に当たっては、時機に応じた重点課題を設定する実施方針を定めるとともに、関係機関(※)等の連携の強化を図る。 (※) 「関係機関」とは、本地域防災計画第5編1-1「防災関係機関一覧表」に記載のある機関、団体をいう。 |