|
第3節 災害情報の収集・連絡活動 |
|
全 部 災害が発生した場合、各防災関係機関(調査責任機関)は直ちに災害時における被害状況調査体制を取り、迅速・的確な被害状況の調査を行う。 1 報告の種別 (1) 概況速報 災害が発生したとき、災害対策本部を設置したとき、又はその他異常と思われる事態(大量の119番通報等)が発生したときは直ちにその概況を報告する。 (2) 被害中間報告 被害状況を収集し、逐次報告するとともに、先に報告した事項に変更のあった場合はその都度変更の報告をする。 (3) 被害確定報告 同一の災害に対する被害調査が終了し、被害が確定したときに報告する。 2 被害状況等の調査と調査責任機関 被害状況の調査は、調査担当課が関係機関及び団体の協力を得て実施する。調査は関係各課相互の連絡を密にし、正確な情報の把握に努めるものとする。なお、被害が甚大であり、村において被害調査が実施できないときは県現地機関等に応援を求め行う。 また、村の対応力のみでは十分な災害対策を講ずることができないような災害が発生したときは、速やかにその規模を把握するための情報を収集するよう特に留意し、被害の詳細が把握できない状況にあっても、迅速に当該情報の報告に努める。 特に行方不明者の数については、捜索・救助体制の検討に必要な情報であるため、住民登録の有無にかかわらず、村の区域内で行方不明となった者について、警察等関係機関の協力に基づき正確な情報の収集に努める。
3 被害状況等報告内容の基準 この計画における被害の程度区分の判定は、法令等に特別の定めがある場合を除くほか、次表のとおりとする。
(注) (1) 住家被害戸数については「独立して家庭生活を営むことができるように建築された建物又は完全に区画された建物の一部」を戸の単位として算定するものとする。 (2) 損壊とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修しなければ元の機能を復元し得ない状況に至ったものをいう。 (3) 主要な構成要素とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部として固定された設備を含む。 4 災害情報の収集・連絡系統 (1) 被害報告等 ア 村は、あらかじめ定められた情報収集連絡体制をとり、村が調査機関として定められている事項については被害状況等を調査の上、被害状況等の部門別及び被害種別の報告様式により、県現地機関等に報告する。 イ 村における体制のみでは、円滑な情報収集連絡の実施が困難であると認められる場合は松本地域振興局長に応援を求める。 ウ 次の場合は、消防庁に対して直接報告する。なお、災害発生後の第一報(即報)は、原則として、覚知後30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で報告する。 (ア) 県に報告できない場合 県との通信手段が途絶するなど、被災状況により県への報告ができない場合には、直接消防庁に報告する。ただし、この場合にも村は県との連絡確保に努め、連絡が取れるようになった後は、県に対して報告する。 (イ) 消防庁に報告すべき災害が発生した場合 火災・災害等即報要領(昭和59年消防災第267号)の「直接即報基準」に該当する火災、災害等を覚知した場合、村及び消防局は、第一報を県に対してだけでなく、消防庁に対しても報告する。(この場合において、消防庁長官から要請があった場合については、第一報後の報告についても、引き続き消防庁に対しても行うことになっている。) 消防庁連絡先
山形村の災害情報連絡系統図 (1) 概況速報 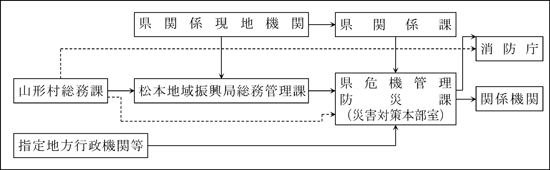
(2) 人的及び住家の被害状況報告 避難準備・高齢者等避難開始・避難勧告・避難指示(緊急)等避難状況報告 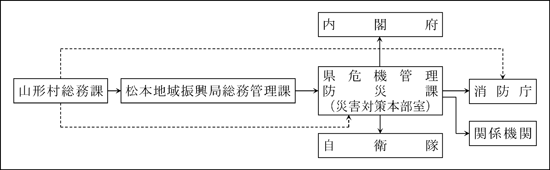
※ 行方不明者として把握した者が、他の市町村に住民登録を行っていることが判明した場合には、当該登録地の市町村(外国人のうち、旅行者など住民登録の対象外の者は外務省)又は県危機管理防災課(災害対策本部)にも連絡する。 (3) 社会福祉施設被害状況報告 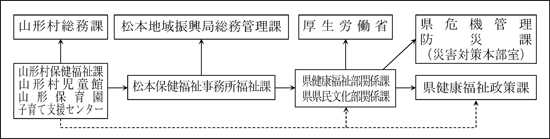
(4) 農業関係被害状況報告 ア 農・畜・養蚕・水産業被害状況報告 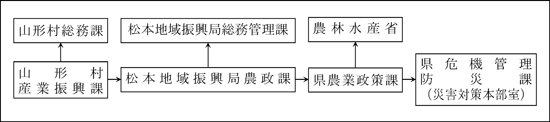
イ 農地・農業用施設被害状況報告 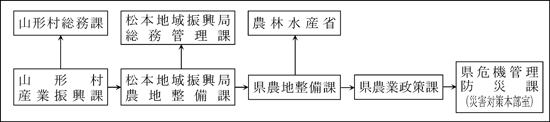
(5) 林業関係被害状況報告 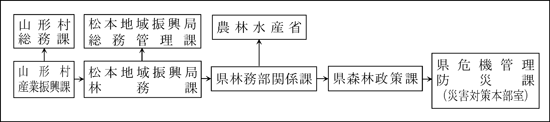
(6) 土木関係被害状況報告 ア 公共土木施設被害状況報告等 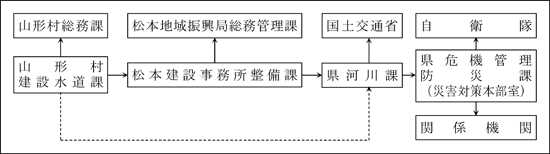
イ 土砂災害等による被害報告 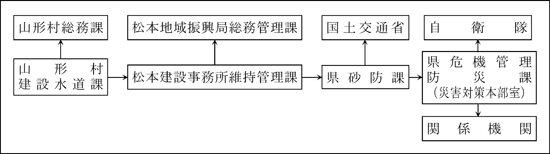
(7) 都市施設被害状況報告 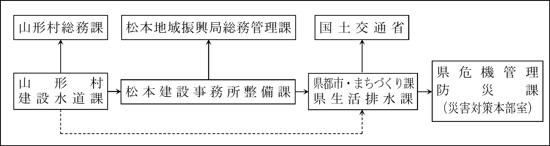
(8) 水道施設被害状況報告 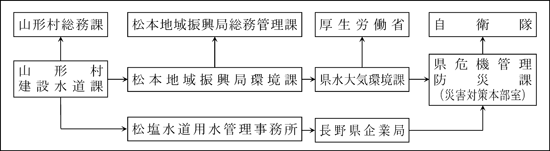
(9) 廃棄物処理施設被害状況報告 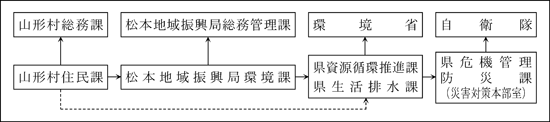
(10) 感染症関係報告 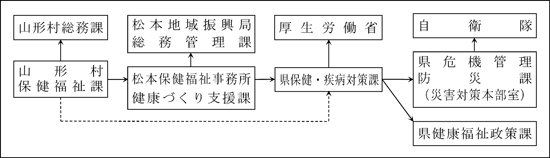
(11) 医療施設関係被害状況報告 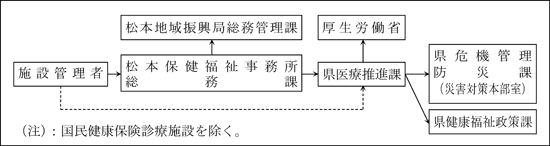
(12) 商工関係被害状況報告 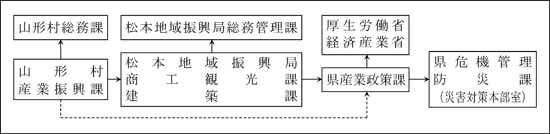
(13) 観光施設被害状況報告 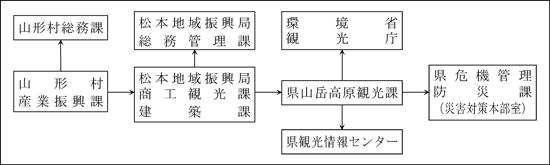
(14) 教育関係被害状況報告 ア 村施設 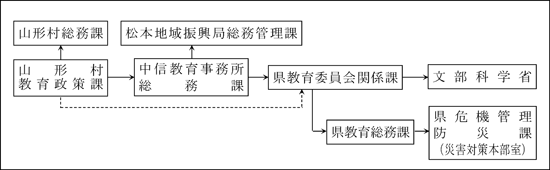
イ 文化財 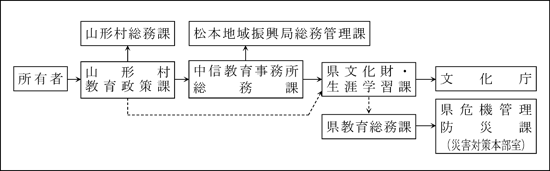
(15) 村有財産 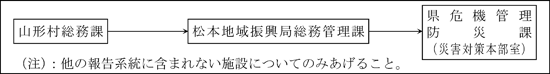
(16) 公益事業関係被害 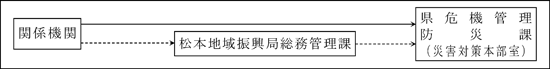
(17) 火災即報 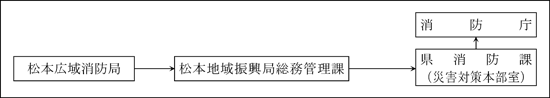
(18) 火災等即報(危険物に係る事故) 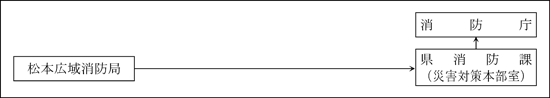
(19) 警察調査被害状況報告 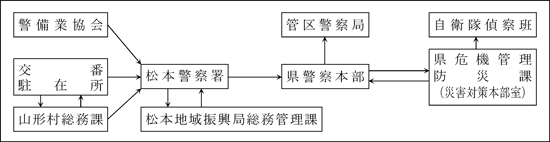
(20) 水防情報 雨量・水位の通報 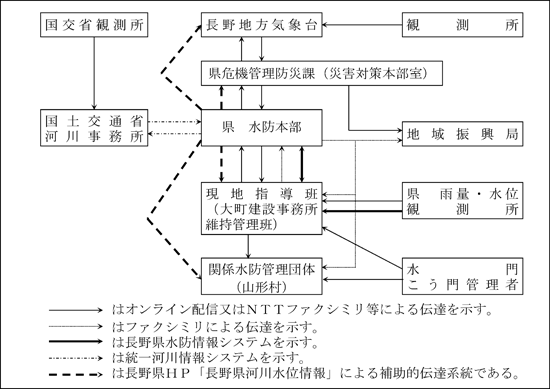
(21) 戸籍、住民基本台帳関係被害状況報告 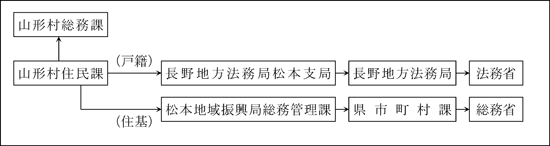
|