|
第22節 危険物施設等応急活動 |
|
総務部 広域消防局 風水害等発生時において、危険物施設等に損傷が生じた場合、危険物等の流出、爆発、火災等により、当該施設関係者及び周辺住民等に重大な被害をもたらすおそれがあることから、当該施設にあっては、施設の点検を速やかに実施するとともに、施設損傷時には応急措置を速やかに実施し、危害の防止を図る。 また、関係機関と相互に協力し、迅速かつ的確な応急措置を行い、当該施設による災害防止及び被害の軽減を図る。 1 共通事項 風水害等発生時において、村は、県及び松本広域消防局と連携し、危険物施設等の損傷等による危険物等の流出、爆発及び火災の発生防止並びに被害の拡大防止等の応急対策を実施し、当該施設の関係者及び周辺住民の安全を確保する。 (1) 災害発生時等における連絡 危険物施設等において災害が発生し又は発生するおそれがある場合における関係機関との連絡体制を確立する。 (2) 漏えい量等の把握 関係機関と連携の上、飛散、漏えい、流出、又は地下に浸透した危険物等の種類、量及びその流出先の把握に努める。 (3) 危険物施設等の管理者等に対する指導 危険物施設等の管理者等に対し、当該施設の実態に応じた応急対策を実施するよう指導する。 (4) 周辺住民への広報の実施 周辺住民に対して広報活動を行い、安全を確保する。 (5) 環境汚染状況の把握 必要に応じて、関係機関と連携して周辺環境調査や水質・大気質の測定を行い、環境汚染状況を的確に把握する。 なお、下流に浄水場等が所在する場合など、危険物等が流入した場合に広範に影響を及ぼす施設等が所在する場合は、重点的に調査を行う。 (6) 人員、機材等の応援要請 必要に応じて、他の都道府県・市町村に対して応援要請をし、応急対策等を行う。 2 危険物施設応急対策 危険物施設の被害状況に関する情報収集に努め、火災、爆発、流出及びそのおそれがあるときは直ちに松本広域消防局に通報する。 (1) 情報収集 危険物施設の被害状況に関する情報収集をし、火災、爆発、流出及びそのおそれ等を把握する。 (2) 危険物施設の緊急時の使用停止命令等 広域連合長は、災害防止等のため緊急の必要があると認めるときは、危険物施設の関係者等に対し、製造所等の一時使用停止又は使用制限を命ずる。 (3) 危険区域の設定等 危険物の流出、火災等により周辺住民に被害が及ぶと予想される場合は、危険区域を設定し、当該区域内の住民の避難、誘導等の措置をとるとともに当該区域内への人及び車両の立入を禁止する。 (4) 資機材の手配 化学消火薬剤、油吸着材等の応急資機材の手配をする。 (5) 関係機関への通報 災害の情報を把握したときは、県危機管理防災課(地域振興局経由)へ通報するとともに、必要に応じ、警察等関係機関へ通報する。 (6) 危険物施設の関係者等に対する指導 危険物施設の関係者、危険物保安監督者、危険物取扱者等に対し、当該施設の実体に応じた応急対策を実施するよう次に掲げる事項について指導する。 ア 危険物施設の緊急使用停止等 危険物の流出、爆発等のおそれがある場合には、操業の停止又は制限をするとともに、危険物の移送の中止及び車両の転倒防止等をする。 イ 危険物施設の緊急点検 危険物施設の損傷箇所の有無等、被害状況を把握するため、緊急点検を実施するとともに施設周辺の状況把握に努める。 ウ 危険物施設における災害防止措置 危険物施設に損傷箇所等の異状が発見されたときは、応急補修、危険物の除去等適切な措置を行い、混触発火等による火災の防止、タンク破損等による油の流出、異常反応、浸水等による危険物の拡散等を防止するとともに、消火設備の起動準備、防油堤の補強等災害発生に備えた措置も併せてとる。 エ 危険物施設における災害発生時の応急措置等 (ア) 応急措置 危険物の流出、火災等の災害が発生したときは、自衛消防組織による現状に応じた初期消火、延焼防止活動及び土のう積み、オイルフェンス等による流出防止措置を迅速かつ的確に行う。 (イ) 消防機関への通報 危険物の流出等の事態を発見した場合は、速やかに消防機関に通報する。 (ウ) 相互応援の要請 必要に応じ、長野県消防相互応援協定に基づき、近隣の危険物取扱事業所に応援を要請する。 (エ) 従業員及び周辺地域住民に対する措置 消防、警察等関係機関と連携し、広報の実施等、従業員及び周辺地域住民の安全確保のための措置を行う。 〔関係機関〕 (1) 危険物の流出、爆発等のおそれがある場合には、操業の停止又は制限をするとともに、危険物の移送の中止及び車両の転倒防止等をする。 (2) 危険物施設の損傷箇所の有無等、被害状況を把握するため、緊急点検を実施するとともに施設周辺の状況把握をする。 (3) 危険物施設に損傷箇所等の異状が発見されたときは、応急補修、危険物の除去等適切な措置を行い、混触発火等による火災の防止、タンク破損等による油の流出、異常反応、浸水等による危険物の拡散等を防止するとともに、消火設備の起動準備、防油堤の補強等災害発生に備えた措置も併せてとる。 (4) 危険物施設における災害発生時の応急措置等 ア 応急措置 危険物の流出、火災等の災害が発生したときは、自衛消防組織による現状に応じた初期消火、延焼防止活動及び土のう積み、オイルフェンス等による流出防止措置を迅速かつ的確に行う。 イ 松本広域消防局への通報 危険物の流出等の事態を発見した場合は、速やかに消防機関に通報する。 ウ 相互応援の要請 必要に応じ、あらかじめ締結されている相互応援協定に基づき、近隣の危険物取扱事業所に応援を要請する。 エ 従業員及び周辺地域住民に対する措置 消防、警察等関係機関と連携し、広報の実施等、従業員及び周辺地域住民の安全確保のための措置をとる。 3 高圧ガス施設応急対策 施設にガスの漏洩や、火災等の災害が発生した場合は、県、消防機関等関係機関と協力して、施設周辺の住民の避難や消火活動等、応急対策を実施する。 (1) 高圧ガス貯蔵施設等においてガスの漏洩、火災等が発生したときは、施設の管理者、従業員とともに、被害の拡大防止のための活動を迅速かつ的確に行う。 (2) 警察、施設の管理者等と協力して、危険区域住民の避難誘導を実施するとともに、危険区域への立入りを禁止する。 〔県〕 (1) 高圧ガス関係事業所に対し、次の応急対策の確立について指導徹底を図る。 ア 施設の保安責任者は、高圧ガス保安法に基づく応急の措置をとるとともに、警察及び消防機関に直ちにその旨を通報すること。 イ 高圧ガスの漏洩、あるいは爆発等のおそれのある施設の配管の弁類等の緊急停止と施設の応急点検と出火防止の措置をとること。 ウ 製造作業を中止し、設備内のガスを安全な場所に移し、また放出し、この作業に必要な作業員の他は退避させること。 エ 貯蔵所又は充填容器が危険な状態になったときは、直ちに充填容器を安全な場所に移すこと。 オ 漏洩ガスが、静電気、摩擦等により発火し、火災が発生した場合には、状況を的確に把握し、火災防止の初期消火に努めること。 カ 災害時には、その状況に応じ、従業員、周辺住民に対して火気の取扱いを禁止するとともに、ガスの種類に応じた避難誘導を行い、特に毒性ガスについては風向を考慮し、人命の安全を図ること。 キ 状況に応じ、長野県高圧ガス地域防災協議会が指定した防災事業所に応援要請すること。 (2) 高圧ガス運送者に対し、次の応急対策について指導徹底を図る。 ア 状況に応じ、車両を安全な場所に移動させるとともに、付近の火気を管理すること。 イ 輸送している容器が危険な状態になったときには、付近の人を安全な場所へ退避させること。また通行者に対する交通遮断をし、状況に応じて安全な場所へ退避させること。 ウ 長野県高圧ガス地域防災協議会が指定した防災事業所に応援要請すること。 4 液化石油ガス施設応急対策 災害時における液化石油ガス一般消費先に対する緊急点検活動及び応急供給活動については、県を通じて長野県LPガス協会に要請する。 また、県及び松本広域消防局と協力して、関係機関、住民等に対し避難誘導等必要な応急措置について指導徹底する。 〔県〕 (1) 液化石油ガス一般消費先に対する緊急点検活動の迅速な実施(特に、病院、避難所となる学校・公民館等及び大規模な容器置場を有する施設等は最優先で実施)について、長野県LPガス協会に要請する。 (2) 容器の流出等のおそれがある容器置場や供給設備について、容器の搬出又は流出防止措置を行うよう、長野県LPガス協会を指導する。 (3) 発災後において、緊急輸送が可能な液化石油ガス充填所を確認し、被災地に対する液化石油ガスの緊急輸送について手配するよう、長野県LPガス協会に要請する。 (4) 被災家庭及び避難所等に対する迅速な液化石油ガス設備の復旧及び臨時供給について、長野県LPガス協会に要請する。 (5) 避難所等で使用するカセット式ガスコンロ及びカセットボンベの調達について、長野県LPガス協会に要請する。 (6) 仮設住宅への液化石油ガスの臨時供給について、他県の応援を含めた対応を、長野県LPガス協会に要請する。 (7) 救援活動により持ち込まれた液化石油ガス容器及びカセットボンベの廃棄又は放置による事故を防止するため、回収と消費者への周知について、長野県LPガス協会に要請するとともに、消費者広報を行う。 連絡系統図 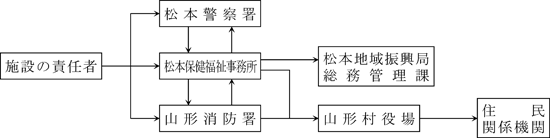
5 毒物、劇物保管貯蔵施設応急対策 (1) 毒物劇物保管貯蔵施設等が風水害等により被害を受け、毒物劇物が飛散、漏洩、流出等により、保健衛生上危害が発生し、又はそのおそれがある場合は、施設の責任者は、直ちに的確な情報を保健福祉事務所、警察又は消防機関に通報するとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な措置をとる。 (2) 周辺住民に対して緊急避難の広報活動を行う。 (3) 飲料水汚染のおそれのある場合は、下流の水道取水地区担当機関及び井戸水使用者、水利権者等への通報を行う。 〔松本広域消防局〕 (1) 毒物劇物による汚染区域の拡大防止措置、危険区域の設定及び立入禁止、避難誘導等の措置を行う。 (2) 中和剤、吸収剤等の使用により、毒劇物の危害駆除を行う。 〔営業者及び業務上取扱者〕 (1) 災害後、直ちに貯蔵設備等の応急点検及び必要な措置を講ずる。 (2) 防災関係機関へ事故発生状況、応急措置等の連絡を行う。 (3) 毒劇物の漏洩、流出、拡散等が発生した場合には、中和剤等による中和除毒及び消火作業により、周辺住民の人命安全措置を講ずる。 6 放射性物質使用施設応急対策 風水害発生時において、放射性物質を使用する施設の損傷等により、放射性物質が露出、流出し、放射線障害の発生又は発生のおそれのある場合は、迅速かつ的確な応急措置の実施により、人命の安全確保を図る。 (1) 放射性物質使用施設において火災が発生し、又は延焼するおそれのある場合、消防機関は、関係機関、放射性同位元素使用者等と連携し、消火又は延焼防止活動を行うものとする。 その際、放射線測定器、放射線保護服等を装備し、放射線障害に備えるものとする。 〔県〕 関係機関と連携し、危険区域住民の避難、誘導措置を実施するとともに、立入禁止区域を設定し、人、車両の立入を禁止する。 |