|
第11節 緊急輸送活動 |
|
総務部 建設水道部 大規模災害発生時の救助活動、救急搬送、消火活動、緊急輸送活動、応急復旧活動等を迅速、的確に実施するために、陸上交通網の確保はもちろん、航空機の活用を含む総合的な輸送確保を行う。 また、緊急輸送活動に当たっては、被害の状況、緊急度、重要度によって判断し、①人命の安全、②被害の拡大防止、③災害応急対策の円滑な実施に配慮して推進するものとし、原則として、次の優先順位をもって実施する。
1 緊急交通路確保のための交通規制 村の管理する道路において、災害が発生し、交通規制の必要が生じたときは、所定の道路標識及び標示板を設置し、交通の安全を図るとともに、禁止又は制限の対象区間、期間及び理由を松本警察署長に通知する。 (1) 実施区分
(2) 規制標識 ア 規制標識は道路法第47条の4(通行の禁止又は制限の場合における道路標識)及び災害対策基本法施行規則第5条(災害時における交通の規制に係る標示の様式等)による。 イ 標識には禁止・制限の対象、区間、期間、理由並びにその他迂回路等を明示する。 (3) 規制の報告 ア 規制時における通報系統は次のとおりとする。 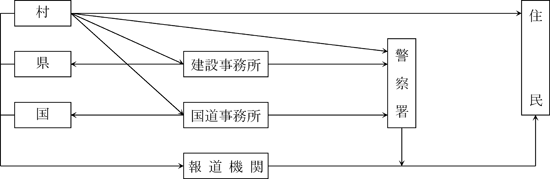
イ 報告、通知内容は禁止・制限の対象、区間、期間、理由並びにその他迂回路の有無等とする。 2 緊急交通路確保のための応急復旧 (1) 応急復旧に当たっては、松本建設事務所、長野国道事務所松本国道出張所等の関係機関と連絡協議し、優先順位を設定してできる限り早期の緊急交通路確保を行う。 (2) 緊急交通路から先の輸送拠点までの取り付け道路や、各避難所までの連絡道路等を確保するため、応急の復旧工事を推進する。 (3) 緊急交通路が使用不能となった場合は、村道、林道、農道等指定道路に代わるべき道路について確保するものとし、この場合、必要に応じて、県等の関係機関に対して応援を要請する。 3 輸送手段の確保 (1) 輸送車両の確保 村は、効率的な輸送体制を確保するために、各部との連絡・調整を行い、村有車両(資料6-2参照)の活用を最大限図るとともに、運転手を確保する。 (2) 応援要請 ア 村は、車両が不足する場合又は災害の状況によりヘリコプターによる輸送が必要な場合は、直ちに県に対して応援を要請する。 また、必要に応じて村内の輸送業者等に要請して、車両及び人員を確保する。 イ 要請に際しては、輸送物資等の内容、数量、出発地、到着地等について、できる限り詳細に連絡する。 (3) 緊急通行車両等の確認 緊急通行車両等の確認事務は、県(知事)及び県警察(公安委員会)において行い、標章(別記様式)及び確認証明書の交付は、地域振興局や警察署、検問所等において行う。 ア 事前届出済証の交付を受けてある車両の取扱い 災害発生後に緊急通行路が指定された際、地域振興局や警察署、検問所等において事前届出済証を提示し、緊急通行車両等の標章及び確認証明書の交付を受ける。 イ 事前届出済証の交付を受けていない車両の取扱い 緊急通行車両等の確認を地域振興局や警察署、検問所等において申請し、確認審査後、緊急通行車両等の標章及び確認証明書の交付を受ける。 (別記様式) 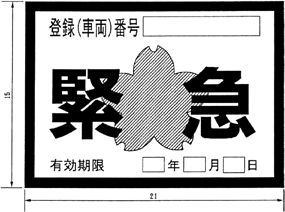
4 輸送拠点の確保 (1) 輸送拠点の運営は、相互応援協定に基づき所在地である市町村が当たることを原則とし、運営に当たっては、村と県は密接に連携する。 (2) 村は、各避難所での必要物資につき、物資輸送拠点(資料6-1参照)と連携を密にする。なお、拠点ヘリポートは、資料6-1のとおりである。 | |||||||||||||||||||||