|
第18節 保健衛生、感染症予防活動 |
|
保健福祉部 消防団 被災後、復旧までの間における被災者の健康の確保を目的として、保健師による被災者の健康状態の把握・健康相談等の保健活動、感染症の発生予防措置・まん延防止措置、栄養士による食品衛生指導、食生活の状況等の把握及び栄養改善対策等の活動を行う。また、被災時の新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等の感染症まん延といった複合災害への対策等の活動も行う。 1 保健衛生活動 (1) 被災者の避難状況を把握し、保健福祉事務所に置かれる地方部保健福祉班に報告する。 (2) 避難所等においては、大規模災害の直接体験や生活環境の変化、生活再建等の不安等により、被災者が精神的不調を引き起こすことが考えられるので、精神相談等を行い、必要に応じて専門病院での精神科治療を受けることができるよう措置する。 (3) 被災者の食料確保のため、炊き出し、その他食品の調達について県に対し報告するとともに、集団給食施設等の復旧活動等を速やかに推進する。 〔関係機関〕 (1) 医師会等は、行政との連携のもとに、医療情報等の速やかな提供に努める。 (2) 看護協会等は、行政との連携のもとに、被災世帯や指定避難所の救護・健康相談を行うように努める。 (3) 栄養士会、食生活改善推進協議会は、行政との連携のもとに、食品衛生指導、栄養指導、炊き出し等を行うよう努める。 〔住 民〕 (1) 医療・保健の情報を積極的に活用し、自らの健康管理に努める。 (2) 住民相互の助け合いを大切にし、自らもボランティアとしての活動を行う。 2 感染症予防対策活動 (1) 災害時の迅速な感染症予防対策に備え、県に準じて感染症予防対策のための組織を明確化するとともに、緊急連絡網、人員配置等事前の感染症予防計画を樹立し、被災時は迅速に対応する。 (2) 災害発生に備え、感染症予防対策用器具の整備及び訓練(含点検)、機材、薬剤等の確保を図る。 消毒用薬剤及び資材等については、通常使用されるものの保管をするとともに、非常時に備えて、購入薬局等を把握しておくものとする。 (3) 感染症発生の予防のための組織を設け、速やかな感染症予防活動が開始できるようにし、県が実施する対策と一体的活動を行う。 山形村感染症対策組織 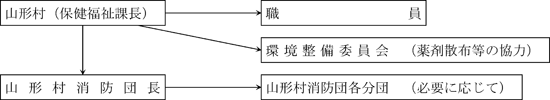
※災害の状況等により、感染症対策班を適宜設置し、人員等必要な人数を保健福祉課で調整する。 ◎感染症対策用機械器具資機材 ・動力噴霧器 2台 山形村役場倉庫 ・肩かけ式噴霧器 1台 山形村役場倉庫 ◎感染症対策用薬剤 消毒液等の薬剤は適当量を備蓄し、不足の場合は、取扱業者から緊急調達するほか、県にあっせん要請を行う。 ◎その他感染症対策用物資及び資機材等 ・テント ・パーテーション ・簡易トイレ ・マスク ・防護服 (4) 感染症の発生を未然に防止するため、松本保健福祉事務所及び関係機関と緊密な情報交換を行い、感染症予防対策をとる。 また、指定避難所の施設管理者を通して、衛生に関する自治組織を編成させ、予防のための指導の徹底を図る。 (5) 災害発生時は、感染症予防活動に要する器具機材の必要量を速やかに算出し、不足分の入手に努める。 (6) 感染症患者又は無症状病原体保有者が発生した場合は、まん延防止のため、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく消毒やねずみ族、昆虫等の駆除等や、予防接種法による臨時予防接種を県の指示に応じて実施する。また、避難所において感染症患者と推定される者及び濃厚接触者が発生した場合には、速やかに避難所内にて隔離し、松本保健福祉事務所を経由して県へ報告する。 (7) 関係団体の協力を得て、災害防疫実施要綱に基づき、感染症発生状況、感染症対策活動状況、災害感染症対策所要見込額をとりまとめるとともに、松本保健福祉事務所を経由して県へ報告する。 (8) 感染症予防活動完了後は、速やかに災害感染症対策完了報告書をとりまとめ、松本保健福祉事務所を経由して県に提出する。 (9) 災害感染症予防活動完了後、災害に要した経費を他の感染症予防活動に要した経費とは明確に区分して把握する。 なお、災害が「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」により、激甚災害及び当該災害に対して適用すべき措置の指定がなされた場合は、必要書類を災害防疫実施要綱に基づき作成し、松本保健福祉事務所を経由して県に提出する。 〔住 民〕 村の行う広報、衛生組織を通しての指導を参考にして、居住地域の衛生の確保に努める。また、避難所においては、村の指導のもと施設管理者が中心となり、衛生に関する自治組織を編成して、感染症予防に努める。 |