|
第1節 火山災害対策 |
|
全 課 第1 災害予防計画 県内及び近隣には活動中の火山が八つあり、比較的、村に近いのは焼岳、乗鞍岳である。これら火山は、距離的にも、爆発・噴火によって甚大な被害を被る危険性は少ないが、その規模によっては、降灰程度の被害は考えられるので、常に万全の注意を払い、災害発生時には迅速かつ的確な応急対策をとる必要がある。 村は、防災の第一次責任を有する基礎的地方公共団体として、火山噴火等にかかわる災害から村の地域、住民並びに一般観光客の生命、身体、財産を保護するため関係機関の協力を得て火山災害対策活動を実施する。特に近年の住宅環境等の変化によりライフラインへの依存度が増大し、災害の及ぼす影響も多様化しており、災害に強いむらづくりが必要となっている。 1 火山災害に強いむらの形成 (1) 総合的・広域的な計画の作成に際しては、火山災害から村土及び住民の生命、身体、財産を保護することに十分配慮する。 (2) 基幹的な交通・通信施設等の整備については、各施設等の耐震設計やネットワークの充実等により、大規模災害発生時の輸送・通信手段の確保に努める。 (3) 住宅、学校や病院等の公共施設等の構造物・施設の安全性の確保等に努める。 (4) 火山災害に強い村土の形成を図るため、治山、治水、砂防事業等を総合的、計画的に推進する。 (5) 老朽化した社会資本について、長寿命化計画の作成・実施等により、その適切な維持管理に努める。 (6) 一部の火山現象については、発生後、短時間で居住地域に到達する可能性があることから、生命に危険のある現象の発生前に、住民等の避難を行うことができる体制の構築に努める。 2 火山災害に対する建築物等の安全性 不特定多数の者が利用する建築物等については、火山災害に対する安全性の確保に特に配慮する。 3 ライフライン施設等の機能の確保 上水道等の施設の火山災害に対する安全性の確保を図るとともに、系統多重化、代替施設の整備等による代替性の確保を進める。 4 降灰対策 活動火山対策特別措置法に基づく施策等を推進することにより、火山噴火に伴う降灰が火山周辺地域の住民の生活等に及ぼす支障を軽減することに努める。 5 災害応急対策等への備え 災害が発生した場合の災害応急対策、災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行うための備えを平常時より十分行うとともに、職員、住民個々の防災力の向上を図るとともに、人的ネットワークの構築を図る。 6 住民に対する啓発 村は、住民に対して、危険防止のための知識の啓発を行うとともに、火山地域にかかる関係機関に、啓発について協力を要請する。 特に、異常現象を発見した場合の通報義務について、啓発を図る。 7 訓練の実施 (1) 防災訓練 村は、防災関係機関及び住民に参加を求め、火山災害の予防又は軽減を期するため防災訓練を実施する。 (2) 通信訓練 村は、火山災害の特殊性にかんがみ、防災関係機関等に参加を求め、各種情報の収集及び通信等にかかる通信体制の確立を期するため、通信訓練を実施する。 第2 災害直前活動計画 火山災害の発生のおそれがある場合に、円滑な災害応急対策が実施できるよう、あらかじめ住民に対する情報伝達体制、避難誘導体制を整備する。 1 住民に対する情報の伝達体制の整備 火山情報等の発表の基準、伝達の経路については、次図のとおりであるが、村は、県及び気象台、周辺市町村、関係機関との連携をとりながら、火山活動に異常が生じた場合には、情報伝達活動が円滑に行えるよう体制の整備を図る。 《焼岳・乗鞍岳に関するもの》 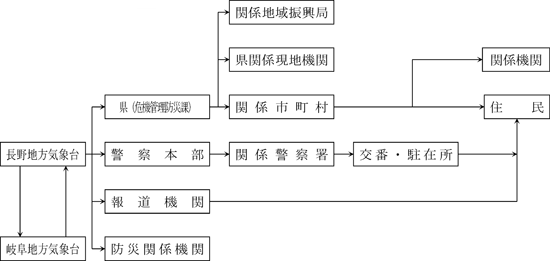
(注1) 「防災関係機関」とは、次の機関をいう。 北陸地方整備局千曲川河川事務所、関東地方整備局長野国道事務所、中部森林管理局中信森林管理署、東日本電信電話(株)長野支店、東日本旅客鉄道(株)長野支店、中部電力(株)松本営業所、東京電力(株)山梨支店、長野電鉄(株) (注2) 「関係機関」とは、各市町村地域防災計画に定める、市町村の機関、(現地機関、消防団、小中学校など)及び防災上関連のある機関をいう。 《異常現象の通報系統図》 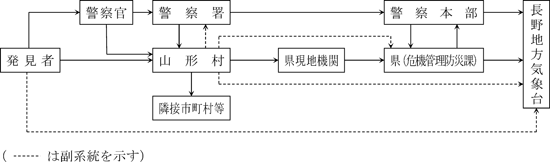
2 避難誘導体制の整備 村は、火山噴火等により住民の生命、身体等に危険が生じるおそれのある場合に、迅速かつ円滑に避難誘導活動が行えるよう、あらかじめ避難計画を作成しておく必要がある。 (避難誘導体制については第2編第1章第12節「避難の受入活動計画」に準ずる。) 第3 災害応急対策計画 火山爆発により地域住民、観光者等が被災し、又は被災するおそれのある場合は、防災関係機関の団体の協力を求め応急の措置を講ずるものとする。 1 災害情報の収集及び伝達 火山災害に関する情報は、応急対策を実施するうえで不可欠のものであるが、現場は、山岳地であり、有線による情報の収集及び伝達は、極めて困難になるものと思われる。したがって県、村、消防機関その他の防災関係機関の無線装置を有効的に配備することによって、情報の収集及び伝達に努める。 収集及び伝達する情報の事項は次のとおりとする。 (1) 人的被害及び住居被害の状況 (2) 要救助者の確認 (3) 住民等の避難の状況 (4) 噴火規模及び火山活動の状況 (5) 被害の範囲等 (6) 避難道路及び交通の確保の状況 (7) その他必要と認める事項 2 救急医療 傷病者に対する応急医療については、第2編第2章第7節「救助・救急・医療活動」によるものとするが、村長は火山災害の特殊性を考慮して傷病者の搬送、一時救護所の設置及び救護班の編成について本計画の定めるところにより実施する。 3 交 通 避難道路及び被災者の救出救急のための交通路の確保については、第2編第2章第11節「緊急輸送活動」による。 4 その他 道路施設が災害を受けた場合、交通の混乱を防止するとともに、本計画に基づき、避難救出・緊急物資の輸送及び防災活動等を効果的に推進する。 |